医薬関係者のための副作用等報告セミナーのご案内
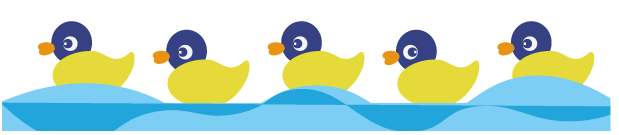 アヒルのコース君
アヒルのコース君
副作用等の報告制度について、概要のほか報告方法や報告に際してのポイント等を説明するセミナーを実施しています。
留意事項
- 原則、オンライン開催として、Microsoft Teamsでの開催となります。
- 開催日時によっては対応できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 受講後、オンラインによるアンケートのご協力をお願いしております。
聴講をご希望の方(申込み方法)
医薬関係者のための副作用等報告セミナーの申込みについて[432.02KB]をご確認の上、ご希望の旨メールにてご連絡をお願いいたします。
- 申込必要事項は「副作用等報告セミナー依頼に関する基本情報」Excel[14.2KB]をご利用ください。
- 講演依頼書は「副作用等報告セミナー依頼状」PDF[97.11KB]をご参照ください。
※救済制度に関する内容をご希望の方は医薬品副作用被害救済制度に関する講演(出前講座)をご参照ください。
制度の趣旨
|
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常、医療の現場においてみられる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用によって発生する健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第68条の10第2項に基づき、医薬関係者が厚生労働大臣に報告する制度です。 |
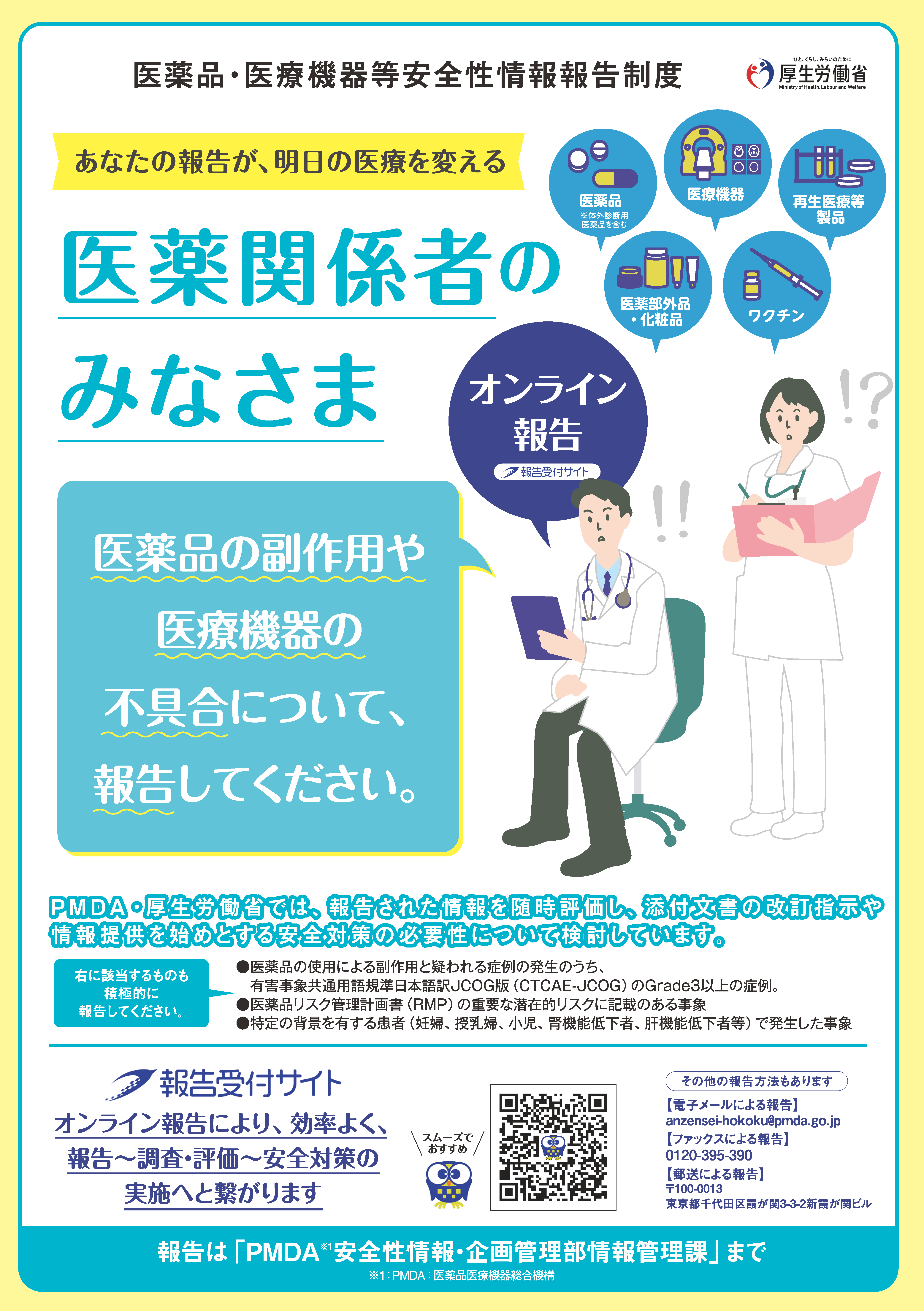 医薬品医療機器等安全性情報報告制度啓発ポスター[805.31KB] (注)商業用印刷(印刷会社での印刷)にかけることは禁止します。 |
報告対象施設及び報告者
すべての医療機関及び薬局等を対象とし、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者その他病院等において医療に携わる者のうち業務上医薬品、医療機器又は再生医療等製品を取り扱う方が報告者になります。
報告対象となる情報
- 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又は不具合の発生(医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発生するおそれのある不具合も含む。)について、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報(症例)
(注)医薬品、医療機器又は再生医療等製品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告をお願いします。
- 医薬部外品及び化粧品についても、健康被害等の情報を知った場合には、化粧品・医薬部外品安全性情報報告書により報告をお願いします。
報告期限
特に報告期限は定められていませんが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告してください。
情報の取扱いと秘密保持
PMDAに報告された情報については、情報の整理又は調査の結果を厚生労働大臣に通知します。また、原則として、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を供給する製造販売業者等へ情報提供いたします。また、PMDA又は当該製造販売業者等は、報告を行った医療機関等に対し詳細調査を実施する場合があります。
報告された情報については、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は公表いたしません。
関連通知
医薬品医療機器等法に基づく、医薬関係者からの副作用・感染症・不具合報告に関連する通知は、以下のとおりです。参考として現在使用されていない通知を過去の通知ページに掲載しています。
| 年月日/種別 | 表題 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)5月16日 事務連絡 |
PMDAの電子報告システム(報告受付サイト)を用いた医薬関係者からの副作用等報告のお願いについて[723.23KB] |
| 2022年(令和4年)3月18日 薬生発0318第1号 |
医薬関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作用、感染症及び不具合報告の実施要領について[282.35KB] |
| 2021年(令和3年)12月6日 薬生安発1206第1号 |
医薬関係者からの医薬品の副作用及び感染症報告について[151.66KB] |
| 2018年(平成30年)6月15日 事務連絡 |
「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」の周知について(情報提供)[1.32MB] |
| 2017年(平成29年)7月10日 事務連絡 |
平成28年度厚生労働行政推進調査事業補助金(厚生労働科学特別研究事業)「薬局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進に関する研究」結果について(情報提供)[1,005.91KB] |
